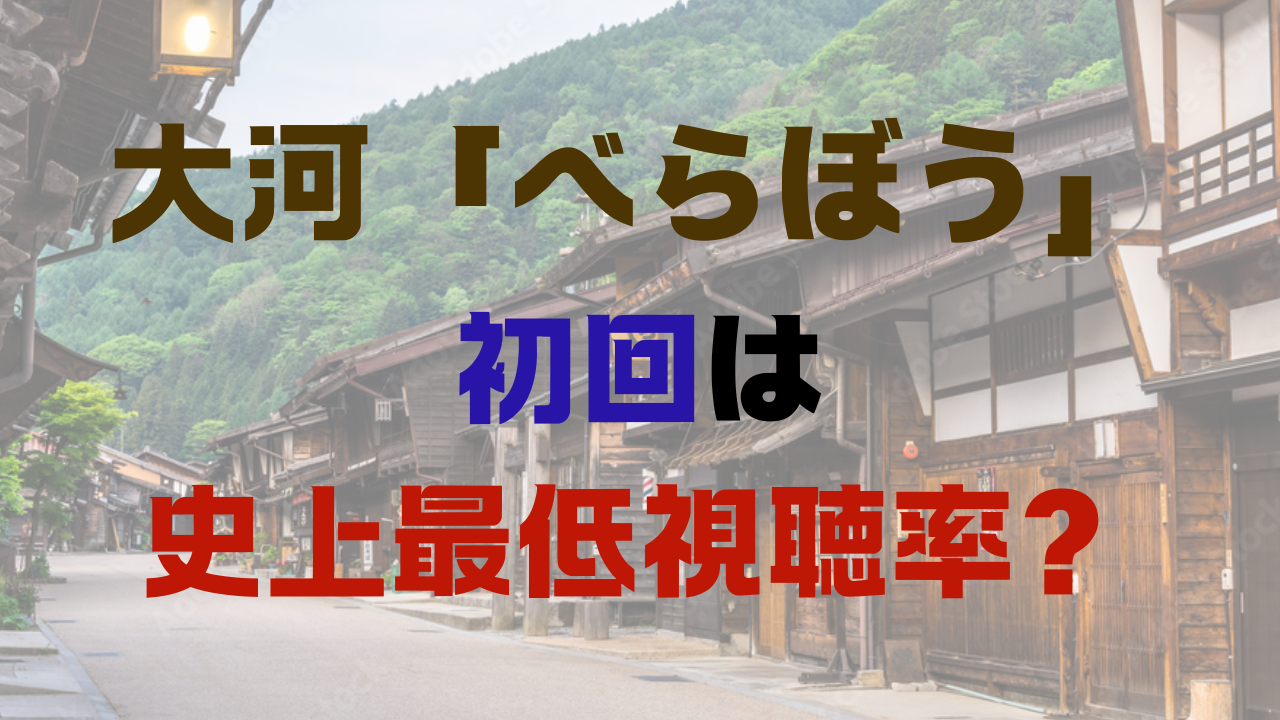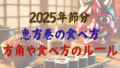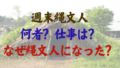2025年の大河ドラマ「べらぼう」は、今までの大河ドラマとは違った描かれ方をしています。そのため、放送前から話題になり注目され、世帯視聴率も気になるところでした。
今までにない「べらぼう」の特徴は…
・江戸時代の「メディア王」が主人公
・知名度の低い人物が主人公
・これまでの大河ドラマとは異なるポップな雰囲気がある
・「吉原」の光と影を描写
・政治、経済、文化を多角的に描写
さて、視聴率は?
1.知名度の低かった蔦屋重三郎が大河ドラマの主人公に選ばれた理由とは?
江戸時代の「メディア王」と言われる蔦屋重三郎ですが、知名度は低く、大河ドラマに取り上げられる前から認知していた人は少なかったのではないでしょうか。
そんな蔦屋重三郎が2025年の大河ドラマ主人公に選ばれたのにはいくつかの理由があります。
1.文化的革新性
・浮世絵、黄表紙、洒落本などの出版を手掛け、江戸時代の文化に大きく貢献してきた。
・葛飾北斎、喜多川歌麿、東洲斎写楽など、多くの才能ある作家や浮世絵師を発掘・育成した。
・「江戸サブカル界隈のフィクサー」として、文化に革新をもたらした。
2.波乱万丈な人生
・吉原で生まれ、「親なし、金なし、画才なし」から江戸時代の寵児へと上り詰めた。
・貧しい環境から、出版業務のトップへと成長した稀有な経歴がある。
・類まれな才能と商才で、文化を牽引している。
3.独自のプロデュース能力
・江戸時代の「メディア王」として知られる。
・大胆な企画力と優れた編集力がある。
・人材を見抜く卓越した目利き力がある。
・当時の庶民の娯楽と社会風刺を同時に提供している。
・サブカル界から教養溢れるコンテンツを発信する、現代のクリエイターと類似している。
・令和時代に共感できる「異色ビジネスドラマ」として魅力的である。
これらの特徴から、蔦屋重三郎は従来の大河ドラマとは異なる、独創的で魅力的な主人公として選ばれました。
2.従来の大河ドラマと一線を画すポップな雰囲気の「べらぼう」にはどんな特徴がある?
1.エンターテインメント性の協調
「笑いと涙と謎に満ちた”痛快”エンターテインメントドラマ」と銘打たれており、従来の重厚な歴史ドラマとは異なるアプローチを取っています。
2.ポップカルチャーの描写
江戸時代のポップカルチャーを牽引した天才プロデューサー・蔦屋重三郎の人生を描くことで、文化や芸術の側面に焦点を当てています。
3.明るく前向きな主人公
主人公の蔦屋重三郎がどこまでもポジティブで明るくパワフルな性格として描かれ、作品全体の雰囲気を明るくしています。
4.テンポの良さ
合戦や戦のシーンがなく、会話のやりとりに重点が置かれているため、テンポ感が良く、視聴者を飽きさせない構成になっています。
5.新しい舞台設定
江戸時代中期や遊郭・吉原が舞台となっており、大河ドラマとしては初めての試みです。
6.軽快な触れ込み
公式サイトの紹介文に「ポップカルチャー」「笑いと涙と謎」といった軽快な表現が使われ、従来の大河ドラマとは異なる方向性を示しています。
このように、ポップな雰囲気により、「べらぼう」は従来の大河ドラマのイメージを覆し、より幅広い層、特に若者層への訴求を狙っていると考えられます。
3.今までにない、誰も知らない遊郭「吉原」の光と影を描写はどんな風に?
誰も知らない遊郭「吉原」の光
1.文化の発信地
吉原は新しい文化や流行を生み出す場所でした。遊女たちはファッションや言葉遣いなど、当時の文化をリードする存在でした。
2.経済の中心
吉原は江戸経済を支える重要な産業の一つでした。遊女たちへの消費は経済の活性化に大きく貢献し、様々な商品やサービスが提供されていました。
3.社会の縮図
身分や階層を超えた人々が集まる場所として、当時の社会の多様性を映し出していました。
誰も知らない遊郭「吉原」の影
1.リアルな表現
NHKの大河ドラマとしては異例の、吉原の暗部を表すショッキングな描写が含まれています。
2.性的描写の大胆さ
全裸シーンなど、これまでの大河ドラマでは見られなかった攻めた性的描写が含まれています。
3.歴史的背景の重視
単なる歓楽街としてだけでなく、当時の社会や文化を映し出す鏡として、吉原が描かれています。
4.エンターテインメント性
「笑いと涙と謎に満ちた”痛快”エンターテインメントドラマ」として、従来の大河ドラマとは異なるアプローチを取っています。
このように、吉原の光と影を鮮明に描き出すことで、視聴者に新たな歴史の一面を提示しています。
4.大河ドラマ「べらぼう」の中で、「吉原の光と影」は物語のどんなな役割を担っているのか?
さて、どのような役割を担っているのでしょうか。
1.主人公の動機付け
蔦屋重三郎は吉原の貧困や女郎たちの窮状を目の当たりにし、これらの「影」の部分を改善しようと奮闘します。
この経験が、彼の行動の原動力となっています。
2.物語の舞台設定
吉原の華やかさと厳しい現実の対比が、ドラマの背景として鮮明に描かれています。
この二面性が、登場人物たちの行動や心理に影響を与えています。
3.社会問題の提起
遊郭の貧困や女郎たちの苦境といった「影」の部分が描かれることで、当時の江戸社会の問題が浮き彫りになっています。
これにより、ストーリーに深みと現実味が加わっています。
4.キャラクターの成長
田沼意次との出会いを通じて、蔦屋重三郎は、吉原の「光」を取り戻すために自己改革の必要性を理解します。
この気づきが彼の成長につながり、ストーリー展開の原動力となっています。
5.文化的側面の描写
吉原が新しい文化や流行を生み出す場所であったという「光」の側面が、蔦屋重三郎の出版事業や文化人との交流につながっていきます。
6.視聴者への問題提起
吉原の「光」と「影」を克明に描くことで、視聴者に当時の社会や人間の本質について考えさせる機会を提供しています。
このように、吉原の光と影はドラマの中核をなす要素として、主人公の動機、物語の展開、そして視聴者への問題提起に至るまで、多層的にストーリーに影響を与えています。
遊郭「吉原」の暗部描写は衝撃的!その描写に賛成?反対?
大河ドラマ「べらぼう」の「吉原」の暗部描写は、視聴者に大きな衝撃を与え、様々な反応が起こりました。
1.衝撃と驚き
NHKの大河ドラマで、これほど露骨な描写が放送されることは今までありませんでした。そのため、多くの視聴者が衝撃を受けました。
2.議論の喚起
遊郭「吉原」の描写、特に女性の扱いについて、視聴者の間で活発な議論が起こりました。
3.批判的な声
一部の女性視聴者から、遊郭を美化しているという批判や、現代の問題意識との関連で厳しい視線が向けられました。
4.リアリティの評価
吉原の苦界としての側面を強く印象付ける描写に、視聴者は感心し、リアリティを評価しました。
5.社会問題への気づき
性産業や人身売買などの現代にも通じる社会問題について考えさせられる機会となりました。
6.歴史認識の深化
江戸時代の「吉原」の実態や、当時の社会構造について、視聴者の理解を深める効果がありました。
7.演出への賛否両論
裸体シーンなどの過激な描写に対しては、必要性を認める意見と批判的な意見の両方が見られました。
このように、「べらぼう」の吉原描写は、視聴者に強い印象を与え、歴史認識や社会問題への関心を喚起する一方で、その表現方法については賛否両論を巻き起こしています。
5.政治、経済、文化について、どのような場面が多角的に描写されている?
大河ドラマ「べらぼう」では、江戸時代後期の政治、経済、文化を多角的に描写する場面が多く見られます。
具体的にはどんな場面でしょう。
政治的側面
1.田沼意次の政策
渡辺謙演じる田沼意次の政治手腕が描かれ、その強引な政策によって幕府の財政基盤を確立する様子が示されています。
2.徳川家のお家騒動
松平武元や一橋治済の暗躍を通じて、江戸時代の権力構造が浮き彫りにされています。
3.寛政の改革
田沼時代の終わりと、それに続く松平定信による寛政の改革が描かれ、政策の変化が蔦屋重三郎の人生にも影響を与える様子が描かれています。
経済的側面
1.江戸の好景気
田沼意次の政策により、江戸が経済的に発展し、文化が活性化する様子が描かれています。
2.出版業の発展
蔦屋重三郎の出版事業を通じて、江戸時代の経済活動や商業の発展が描かれています。
3.吉原の経済状況
遊女たちの窮状や、吉原の経営不振が描かれ、当時の経済格差や社会問題が浮き彫りにされています。
文化的側面
1.文化人との交流
蔦屋重三郎と平賀源内や北尾重政といった文化人との交流を通じて、江戸時代の文化的ダイナミズムが描かれています。
2.浮世絵の発展
葛飾北斎や喜多川歌麿、東洲斎写楽といった浮世絵師との関係を通じて、日本美術史における重要な出来事が描かれています。
3.江戸の食文化
「百川」の折詰弁当など、江戸時代の贅沢な食文化が描かれています。
4.出版文化
蔦屋重三郎による吉原のガイドブックやPR本の制作を通じて、江戸時代の出版文化の発展が描かれています。
これらの描写を通じて、「べらぼう」は江戸時代後期の政治、経済、文化について多角的に描き、視聴者に当時の社会の複雑さや豊かさを伝えています。
6.「べらぼう」の視聴率は最高?最低?どうだった?
大河ドラマとして様々な特徴がある「べらぼう」ですが、現時点での視聴率は以下の通りです。
1.初回視聴率:12.6%(世帯平均視聴率)、7.3%(個人視聴率)
2.第2回:12.0%
3.第3回:11.7%
この視聴率は、近年の大河ドラマの中では最低水準となっています。
特に初回視聴率は、前作「光る君へ」の12.7%を0.1ポイント下回り、1963年の「花の生涯」以来の大河ドラマ初回視聴率として歴代最低を記録しました。
しかし、従来のテレビ視聴率だけでなく、NHKプラスでの視聴も注目されています。
「べらぼう」の初回放送は、NHKプラスの全ドラマの中で最多となる72.8万ユニークブラウザ(視聴者数に相当)を獲得しました。
また、BSを含めたテレビ放送の視聴人数は2125.4万人に達しており、従来の視聴率だけでは測れない新たな視聴傾向がうかがえます。
大河ドラマ「べらぼう」の視聴率が低いと考えられる理由6つ
1.遊郭が舞台であることの抵抗感
吉原が主要な舞台となっているため、特に女性視聴者から敬遠された可能性があります。
2.若年層の視聴率の低さ
特に男性20~34歳の視聴率が1.1%と極めて低く、若い世代の関心を引きつけられていませんでした。
3.戦闘シーンの不在
名将や名将軍が登場しないため、特に男性視聴者の興味を引きにくい構成となっています。
4.時代設定の難しさ
江戸時代中期という設定が、現代の視聴者にとって親しみにくい可能性が考えられます。
5.子育て世代の懸念
「女郎」などの用語の意味を子どもに説明しづらいという声が子育て世代から上がっています。
6.従来の大河ドラマとの違い
戦国時代や幕末など、より馴染みのある時代設定の大河ドラマと比べて、親しみやすさに欠ける可能性があります。
一方で、NHKプラスでの視聴は好調であり、若い世代からの支持も得ています。従来のテレビ視聴率だけでなく、配信サービスでの人気も考慮する必要があると言えます。
まとめ
2025年大河ドラマ「べらぼう」のテレビの世帯視聴率は歴代最低の視聴率を記録しましたが、NHKプラスなど他の媒体での視聴もされているため、単純に”最低視聴率”と言い切ることができないと言えるでしょう。