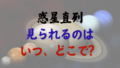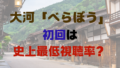近年、節分の日に恵方巻を食べる人が増えてきました。
さて、今年2025年の節分はいつなのか、恵方巻を食べる日や方角、食べ方について紹介していきます。
1.2025年の恵方巻を食べる際の方角(恵方)は?
2025年の恵方巻を食べる際の恵方の方角は、西南西(にしなんせい)です。恵方巻は節分の日に食べる風習で、その年の恵方(縁起の良い方角)を向いて無言で丸かじりすることが良いとされています。
恵方は年によって変わり、十二支の方角に基づいて決められます。2025年は乙巳(きのとみ)年で、十二支では巳(み)年にあたります。巳年の恵方は西南西となります。具体的な角度としては、真西から約30度南に傾いた方角が西南西となります。
恵方巻を食べる際は、コンパスアプリなどを使って正確な方角を確認するとよいでしょう。
恵方の決まり方
恵方巻の方角は毎年変わります。恵方巻を食べる際の方角(恵方)は、その年の干支の十干に基づいて決定されます。恵方の変化には次のようなパターンがあります。
1.5年周期
恵方は5年ごとに同じ方角に戻る傾向があります。
2.4つの主要方角
恵方は主に東北東、西南西、東南東、西北西の4つの方角を循環します。
3.十干による決定
恵方は十干(じっかん)という10年周期の暦法に基づいて決められます。
具体的に、恵方の決定方法は以下のようになっています。
・甲(きのえ)の年とその5年後(己の年)……東北東と東の間
・丙(ひのえ)の年とその5年後(辛の年)……南南東と南の間
・戊(つちのえ)の年とその5年後(癸の年)…南南東と南の間
・庚(かのえ)の年とその5年後(乙の年)……西南西と西の間
・壬(みずのえ)の年とその5年後(丁の年)…北北西と北の間
「十干」は10年周期なので、西暦の下一桁とちょうど対応していることがわかります。
つまり…
西暦の下一桁が0の年…庚の年→西南西と西の間
西暦の下一桁が1の年…辛の年→南南東と南の間
西暦の下一桁が2の年…壬の年→北北西と北の間
西暦の下一桁が3の年…癸の年→南南東と南の間
西暦の下一桁が4の年…甲の年→東北東と東の間
西暦の下一桁が5の年…乙の年→西南西と西の間
西暦の下一桁が6の年…丙の年→南南東と南の間
西暦の下一桁が7の年…丁の年→北北西と北の間
西暦の下一桁が8の年…戊の年→南南東と南の間
西暦の下一桁が9の年…己の年→東北東と東の間
ということがわかります。
よって、今年2025年の恵方は西南西(正しくは西南西と西の間)ということがわかります。
この変化は、日本の伝統的な暦法や陰陽道の考え方に基づいており、毎年新しい運気を取り入れる機会を提供していると考えられています。
2.恵方巻を食べる時のルールは9つ、それは何?
恵方巻を食べる際には、ルールがいくつかあります。
1.切らずに丸ごと食べる
恵方巻は1本丸ごと食べるのが基本です。これは「縁を切らない」という意味があります。
2.その年の恵方を向いて食べる
2025年の場合は、西南西を向いて食べます。
3.黙って食べる
食べている間は話さないようにします。これは、話をすると「福が逃げる」と言われているからです。
4.願い事をしながら食べる
心の中で願い事を唱えながら食べるとよいとされています。
5.節分の日に食べる
2025年の場合は、2月2日が節分です。
6.途中でしょうゆをつけない
食べ始めたら最後まで口から離さないのが理想的です。
7.食べる時間は自由
節分の日であれば、朝でも夜でも好きな時間に食べて構いません。
8.おまけのルール1:目を閉じて食べる
神社で参拝するように、深く願いを込める意味があります。
9.おまけのルール2:笑顔で食べる
「笑う門には福来る」という考えに基づいています。
これらのルールは縁起を担ぐためのものです。なので、すべてを厳密に守る必要はなく自分なりの方法で楽しく食べるのが一番です。
恵方巻を黙って食べるよ良い理由は?
恵方巻きを黙って食べる理由には、いくつかの説があります。
1.福を逃がさないため
恵方巻きは「福を巻き込む寿司」とされており、話すことで福が逃げてしまうと考えられています。
2.願い事に集中するため
神社やお寺でのお参りのように、無言で心の中で願い事を唱えることで、より効果的に願いを込められると考えられています。
3.鬼に聞こえないようにするため
節分の行事の一環として、鬼に願い事や福を奪われないよう、静かに食べるという説もあります。
4.神事としての意味合い
「無言」は神事につきものであり、恵方巻きを食べる行為も一種の神事として捉えられています。
これらの理由から、恵方巻きを食べる際は無言で食べることが伝統的な作法とされています。
ただ、一番大切なのは、楽しみながら食べることです。
恵方巻を笑って食べると良い理由は?
恵方巻きを笑って食べる理由には、いくつかの意味があります。
1.福を呼び込む
「笑う門には福来る」ということわざのように、笑顔で食べることで幸運や福を引き寄せると考えられています。
2.邪気を払う
笑うことで邪気を払い、良い運気を招くとされています。
3.和やかな雰囲気を作る
笑顔で食べることで、家族や周囲の人々と楽しく節分を過ごす雰囲気を作り出します。人間関係の絆を深める効果も期待できるとされています。
4.地域の風習
関西地方の一部では、笑いながら恵方巻を食べると幸運が訪れるという伝統があります。
5.五行思想に基づく
笑いは「火の気」を象徴し、「金の気」を和らげる効果があるとされ、新年の祝いに適していると考えられています。
6.ストレス解消
笑うことでストレスホルモンが減少し、リラックス効果が得られます。
7.願望成就への期待感
笑顔で恵方巻きを食べることで、一年中幸運が続くという願いが込められ、前向きな期待感を持つことができます。
ただし、恵方巻きを笑って食べる習慣は地域によって異なり、一般的には黙って食べるのが基本とされています。
多くの場合は、食べる前に笑顔を見せてから、静かに食べ始めるという方法が推奨されています。
3.恵方巻に入れる具材は何がある?
恵方巻に入れると良い具材は?縁起の良いものを入れると良い?
恵方巻きに使用される具材は、縁起を担いだものが選ばれています。日本では食材に込められた意味が重要視され、特に節分においては、これが一層強調されます。
具材に込められた意味として、7という縁起のいい数字や七福神にちなんで、7つの具材を使用しています。
そして恵方巻きに用いられる伝統的な具材には、うなぎ、きゅうり、卵焼き、シイタケ、カンピョウ、桜でんぶ、そして海老などが含まれます。
これらの具材にはそれぞれ、健康、繁栄、長寿などの願いが込められているためです。
| うなぎ | 細長い形状から「長寿」「上昇」「出世」 |
| きゅうり | 「9つの利」をもたらす、「永遠」、 種が多いから「繁栄」、緑色は「若さ」「健康」を象徴 |
| 卵焼き | 黄色い色から「豊かな財」「金運上昇」、 巻かれた形状から「巻き込む」→「福を巻き込む」 |
| しいたけ | 陣笠に似た形から「身を守る」「家族を守る」 「志(しい)」「高(たけ)」→「志が高い」という言葉遊び |
| かんぴょう | 細長い形状から「長生き」、絆や結びつき、 「巻く」→「福を巻き込む」という意味もある |
| 桜でんぶ | 「めでたい」(原材料の鯛から語呂合わせ) ピンク色は「桜」を連想→「春」や「新しい始まり」を象徴 「でんぶ」→「伝舞(でんぶ)」→「福を伝える」という意味があるとされる |
| えび | 「めでたい」「健康長寿」「繁栄」 |
これらの具材を組み合わせることで、恵方巻全体として「福を巻き込む」という意味が込められています。
この恵方巻きを食べることで、それぞれの願いを体現し、節分の日に特別な意味をもたらします。
恵方巻の人気具材は?
恵方巻に入れると良い7つの具材について紹介しましたが、そうは言っても、好きなものやおいしいものを食べたい気持ちはあります。
例年の販売傾向や街頭アンケートなどから、人気具材のランキングを紹介します。
1.海鮮巻
最も人気が高く、認知度も高い。2022年の調査では57.0%の喫食率を記録し、1位となっています。
2.ネギトロ巻
2023年の調査では2位にランクアップし、39.9%の喫食率を示しています。
3.サーモン巻
2023年の調査では36.7%の喫食率です。
4.鉄火巻
5.サラダ巻(ツナ・レタスなど)
6.和風海苔巻(かんぴょう、しいたけ、卵焼きなど)
7.お肉巻(ビビンバ、ローストビーフなど)
8.揚げ物巻(カツ、エビフライなど)
9.ヘルシー巻(雑穀米、蒸し鶏など)
これらの数値は年々変動しており、新しい種類の恵方巻も登場しています。
全体的な傾向として、伝統的な具材を使用した恵方巻から、より多様な具材を使用した新しいタイプの恵方巻へと認知度が広がっていることがわかります。
4.恵方巻の習慣はいつから始まった?起源は?恵方巻の変遷は?
恵方巻きを黙って食べる習慣は、日本の文化、特に関西地方の文化から始まったものと言われています。
1.発祥地
大阪を中心とする関西地方が起源
2.文化的・伝統的な意味
・歳神様(としがみさま)をお迎えする習慣と関連
・「福を逃さない」「縁を切らない」という考えや願い事を心に秘めるという意味がある
・恵方巻きを黙って食べる習慣は、日本の伝統的な風習と現代の商業的展開が融合して生まれた、独特の文化現象と言える
3.江戸時代中期
節分の時期に香の物入りの巻き寿司を恵方を向いて食べる習慣から発展
4.幕末から明治時代初頭の大阪・船場
・商売繁盛、無病息災、家内円満を願って始まったとする説
・船場の色街での風習から広まったとする説
5.昭和初期~中期
大阪の海苔やすしの組合が販促のため広げる
6.1980年代以降、促進戦略により、全国的に広まる
ただし、これらの説はチラシや聞き取りが出典であり、明確な史実としての裏付けは乏しいです。
恵方巻の認知度ランキング
恵方巻の習慣、認知度が高い都道府県を紹介します。
1.大阪府
・恵方巻の発祥地とされ、最も認知度と普及率が高いです。
・長年の伝統があり、多くの住民が恵方巻を食べる習慣を持っています。
2.京都府
・大阪に隣接し、関西文化圏の中心地の一つとして高い認知度を示しています。
3.兵庫県
・特に神戸市を中心に、恵方巻の認知度が高くなっています。
4.滋賀県
・関西圏に属し、恵方巻の文化が浸透しています。
5.奈良県
・関西圏の一部として、恵方巻の認知度が高い県の一つです。
6.和歌山県
関西圏に含まれ、恵方巻の文化が広く知られています。
7.東京都
大都市圏として、コンビニエンスストアやスーパーマーケットの販売戦略により高い認知度を示しています。
これらの県は、主に関西圏とその周辺地域、および大都市圏に集中しています。ただし、近年では全国的に認知度が上がっており、多くの県で恵方巻が知られるようになっています。
一方、恵方巻の認知度が比較的低い県は、こちらになります。
1.東北地方
青森県、秋田県、岩手県、山形県
2.北海道
特に道東や道北の地域
3.九州地方
宮崎県、鹿児島県
4.四国地方の一部
高知県
これらの地域で認知度が低い理由として…
・恵方巻の文化が関西から広まったため、地理的に遠い地域では浸透が遅れている
・地域固有の節分の習慣や食文化が根強く残っている
・恵方巻の文化が浸透する前から、独自の節分行事が定着している可能性がある
・都市部と比べて、コンビニエンスストアやスーパーマーケットの販売促進活動の影響が少ない
・若年層の人口比率が低い地域では、新しい習慣の浸透が遅い傾向にある。
以上のことがいえます。
しかし、近年では全国的に認知度が上昇しており、これらの地域でも徐々に恵方巻が知られるようになっています。また、若い世代を中心に認知度が高まっていると言えます。